April 03, 2017
荷風さんの昭和
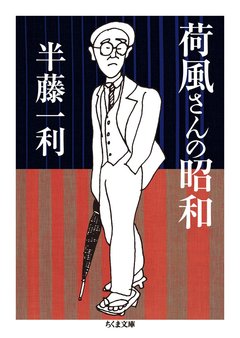 荷風さんの昭和 (ちくま文庫)
荷風さんの昭和 (ちくま文庫)
昭和34年4月30日未明、荷風が他界した。その年の4月に創刊された週刊文春の編集部に配属されたばかりの半藤一利がいた。荷風急死の一報を受け、市川の自宅に駆けつけ、警察による検死から納棺まで一部始終を見届け週刊文春の特集記事を書いたのが他ならぬ本書の著者・半藤一利であった。歴史探偵を自称する氏が、孤高の自由人・永井荷風の目を通して戦前、戦中、戦後の昭和を検証する。本書が上梓されたのが1994年、時は細川内閣の時代、1937年日中戦争に突入した時の内閣総理大臣近衛文麿の孫の登場に歴史探偵は一抹の不安を隠せなかったようだ。本書の発行から23年を経て、政治は益々劣化の速度を速め、時代の空気感は戦前へ回帰するような不穏な動向を露わにしている今日、荷風さんに倣い昭和史を斜に構えて見直してみよう。
本書に『断腸亭日乗』から引用されている一文だけ選ぶとすれば昭和11年2月14日の此れだろう。
《日本現代の禍根は政党の腐敗と軍人の過激思想と国民の自覚なき事の三事なり。政党の腐敗も軍人の暴行も、之を一般国民の自覚に乏しきに起因するなり。個人の覚醒せざるがために起こることなり。然り而して個人の覚醒は将来に於いてもこれは到底望むべからざる事なるべし。》今もって説得力のある荷風の言葉である。それも2.26事件の12日前に書かれていた。
----------------------目次----------------------
序章:一筋縄ではいかぬ人
第一章:この憐れむべき狂愚の世―昭和三年〜七年
第二章:女は慎むべし慎むべし
第三章:「非常時」の声のみ高く―昭和八年〜十年
第四章:ああ、なつかしの〓(ぼく)東の町
第五章:大日本帝国となった年―昭和十一年
第六章:浅草―群衆のなかの哀愁
第七章:軍歌と万歳と旗の波と―昭和十二年〜十四年
第八章:文学的な話題のなかから
第九章:「八紘一宇」の名のもとに―昭和十五年〜十六年
第十章:月すみだ川の秋暮れて
第十一章:“すべて狂気”のなかの正気―昭和十六年〜二十年
終章:どこまでもつづく「正午浅草」
--------------------------------------------
そういえば、第六章にもその固有名詞が出てくるが、10年ほど前のこと吉原御免状ミニダイブで廓の堀跡周辺を徘徊している時に京町二丁目の羅生門河岸の外で隣地が更地となった建物の遣れたトタンの外壁写真を撮っていた時である。更地となった建物の関係者の年輩の御婦人が現場の様子を見に現れた。その御婦人の話によると荷風さんが日記にも書いていた吉原のナポリがあった場所だと云う。何でも荷風さんは店の奥の和室で昼寝をしたりするほどの常連だったとか...荷風さんを知る人から話しが聞けたのは貴重な体験でした。